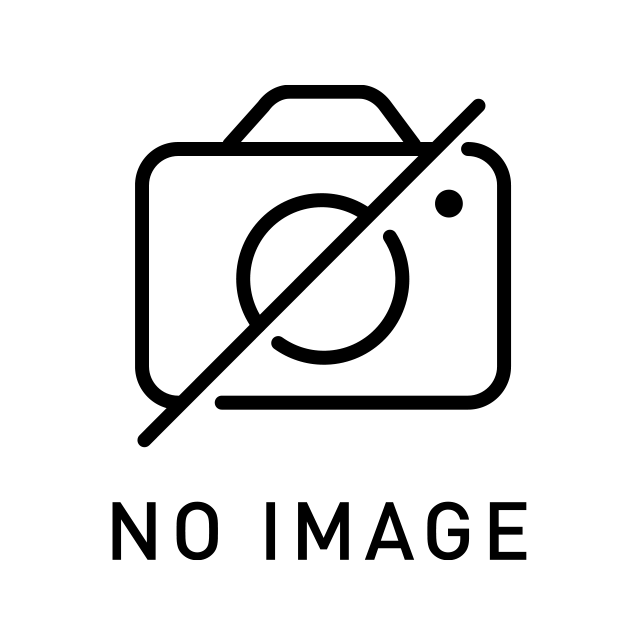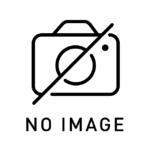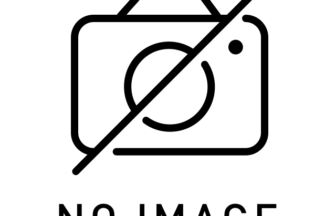杉浦さんがこれまでどのようにお仕事をされてきたのか教えていただけますか?
中学、高校の頃からラジオはAM・FM問わず聞いていたのですが、ラジオで喋っている人と自分とは縁遠い別世界の人だと思っていました。なので、まさか自分がなるとは思っていませんでした。
目指したきっかけは、大学卒業に伴う就職のときでした。大学に通っているときに論文の発表会で賞を取ったことがあったので、僕は文章を書くライターになりたいと思うようになっていました。当時はウェブライターのような仕事が存在しないので、「ライターってどうやってなるんだろう」「出版社に入ればライターになれるのかな?」みたいに漠然と考えていました。そんなとき、僕は相変わらずラジオを聴いていたので、「ラジオも言葉で何かを伝えることができるという意味では一緒だ」と思ったんです。世の中は就職氷河期の真只中で、なかなか就職が決まらない周りの人たちは、「どの会社に行きたい」「どんな仕事に就きたい」ではなく、「どこかに就職できればいい」という目的に変わっていきました。
自分はそういうのが嫌で、自分の仕事は自分で選びたいという気持ちがあってラジオパーソナリティーになりました。
杉浦さんが仕事をしていて、やりがいを感じるポイントはありますか?
やりがいを感じるポイントはいっぱいありますよ。ラジオなどで自分が発したことに対して聴いた人からリアクションをもらえるというのは純粋にすごく嬉しいです。イベントとかでステージに出たときもそうなのですが、お客さんに何か言葉を投げかけたときに、大きなリアクションでなくとも「うんうん」と頷いてもらえるだけでも嬉しくなります。お返しの反応をもらえるということが、日々のやりがいみたいなところはあります。
あと、この仕事をしていて面白いと感じることは、別の仕事で得た経験が良い方向に影響し合うところです。普段の僕は、職業をきかれたらラジオパーソナリティーと答えるのですが、他にも司会をしたり、子レーションやリポーターをしたり、ときには実兄がたいなこともしています。声の仕事を缶々やっている中で、それぞれ求められているものが少しずつ違うのですが、意外なところの共通点がそれぞれの仕事に良い影響を与えることがあるのです。
例えば、テレビの仕事をしていたからラジオの仕事がやりやすくなりました。テレビでは、本番中のカメラに映らないところで「カンペ」という進行用の大きな紙が表示されます。初めてテレビに出させて頂いた僕は、ついカンぺの文字を読んでしまいました。本当はパッと一瞬だけ見て、すぐにカメラへ視線を戻して喋らないといけないのですが、それがとても難しく苦労しました。そのような仕事を何度も経験して、カンペをあまり見ずにカメラ目線を意識できるようになったとき、ラジオの仕事にも変化がありました。本番中に原稿を見ながら喋っている最中でも、「今、スタッフはどうかな?」と周りの様子を伺うことができるようになったのです。ガラス張りのサテライトスタジオの仕事では「外の人はどんな感じかな?」とリスナーの姿を確認できるようになりました。いろんなことをやると少し視野が広がっていき、思っても見ないものが見えてくるようなことは結構あります。
杉浦さんが今後やっていきたい仕事はありますか?
それこそ僕の仕事観じゃないですけど、何かこういうのをやりたいというより、何でもやりたいですね。求めてくださるのでしたら「何でもやります」という感じです。
杉浦なおや
1979年12月11日生まれ滋賀県を拠点に活動中主な仕事としてラジオDJやイベントの司会を行っている。趣味はソロキャンプ・料理・ランニング。
主な出演歴 FM 滋賀 キャッチ! FM-MOOV KOBE HEARTY RADIO 他多数
これからの福祉
分け隔てはいらない。最後までやるという意志や集中力はすごい武器。
就労支援という場所に対して思うことですが、僕自身はそういった分け隔てはいらないと考えています。なぜなら、そういう作業所に通っている方や、シェイクハンズ(大津市にある就労支援事業所)に通っている方にも、僕では思いもつかないようなことをやっていたり、すごい能力を持っていたりするじゃないですか。
初めてシェイクハンズにお伺いさせて頂いた時、世界の有名な建築物の写真をパソコンのデザインソフトの直線ツールだけで模写している人がいらっしゃいました。僕自身も同じデザインソフトを使う機会があるので、線だけで写真を模写することがいかに大変なのかが分かるんです。その集中力とか、一個のことをちゃんと地道に、着実に仕上げられる能力を持っていることはすごいと思います。僕らだったらきっと途中でやめてしまうじゃないですか。
「やろう!」「しんどいけど最後の完成形まで持っていこう!」という意志や集中力というのは本当にすごい武器なんです。
福祉をもっとオープンに。
先ほどの京都にある作業所さんのお祭りは社会と繋がるすごくいい機会だと思います。一般の人も一緒に一つのお祭りを楽しみながら、みんな繋がれるじゃないですか。でも、すごくいい機会だと思う反面、そういうことを年に一回でも頑張って作業所の方でお祭りを開かないと、その隣の人たちに認知されないという現状も感じていました。そこには複雑な思いがありました。本当だったら、そういうお祭りを開かなくても、その地域のコミュニティにちゃんと溶け込み、周りの人もちゃんと知っている。そういった理想のかたちになって欲しいと思います。
「何かが出来ない」というのは個性。
それそれの長所や個性を推し出せるようになればいいですね。
「何かができない」ということは、その人の個性だと思っています。僕は喋ることはできても、演技することはできないんです。できるできない、得意不得意っていうのは誰にもありますよね。それと全く同じとは言い切れないのですが、同じ土台で「何かができない」も考えてみたいのです。
素晴らしい能力を持っているのだから、それを活かせる適材適所のような場所がどこかにあると唐じています。日本では、なんとなく、みんな一緒じゃないといけない、という空気があります。「同じ部署で同じ仕事をしている人は、同じ能力を持っていないといけない」という考えを持っている人がいることを感じることがあります。そうではなくて、もっとそれぞれの長所や個性を推し出せるようになればいいですね。
僕らがやっているラジオも、月曜日から木曜日まで違うパーソナリティが喋っていて、それぞれのカラーが生まれることが良かったりします。毎日が同じカラー、同じ雰囲気でいいならラジオパーソナリティは一人でいいですよね。四人いるなら、四人それぞれのカラーを出せたらいいですし、だからこそ毎日ラジオを聴く面白さがあります。
だから、就労支援に通われる方をはじめとした障がい者の能力や個性はすごく可能性を感じますし、そういう人材が欲しいところはマッチングを求めていると思います。しかし、現状ではそこがまだうまく噛み合っていないとも感じます。
身構えなくて大丈夫です。一緒に福祉を盛り上げでいきましょう!
初めに話した京都にある作業所さんのお祭りは決して大きい
イベントではなかったですし、イベントの企画会社もいませんでした。作業所さんが手作りで開催されているイベントでしたので、一日の進行台本がA4の紙一枚でした。それぐらいでも大丈夫です。事務所のHPはもちろん、SNS もやってますのでそちらからでも大丈夫です。まずは気軽に相談してもらえればと思います。一緒に福祉を盛り上げて行ければと思います!