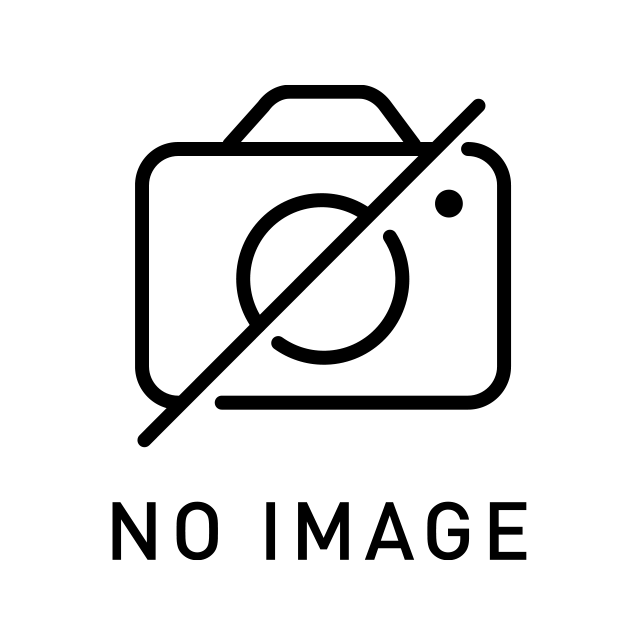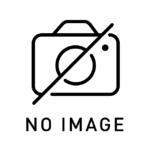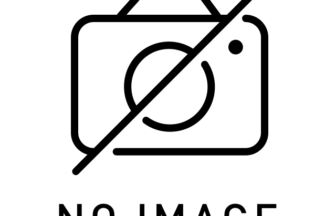自分が今持っている感情・思想は先天的なものか、はたまた後天的なものなのか。
自分の心と素直に向き合うそんなエッセイコーナーです。
今回は、漫画やゲームを通して自分自身だけではなく社会にも目を向けたそんなお話です。
性格基盤に激震が走る
人生に影響を与えるほどの名著は数あれど、趣味や思考・行動ではなく、性格に影響を与える作品というのはそう出会えるものではない。その理由は、性格が目的のための道具ではないからだ。
趣味や思考・行動は、娯楽や交流のため、そして問題解決や物事を理解するための手段でもある。
具体的だから意識しやすいし、役に立つから身につける動機がある。
けれども、性格はどちらかといえば目的を生み出す側のものだ。何かのために優しい行動を心がけたり、優しい行動をとるための思慮深さを身につけたりすることはできる。しかし、最初の過程である「何かのために」の基盤となるのは性格だ。例えば、他のものにあまり興味がわかない性格なら、そもそも優しい行動をとろう!という思考が生まれないかもしれない。このように自身の根幹である性格が、一つの作品から影響を受けることはなかなかないだろう。
しかしながら、僕のそんな性格を変えてしまった作品がある。それが『さよなら絶望先生』という作品だ。
ポジティブなあまのじゃくの誕生
主人公で学校教師の糸色望(いとしきのぞむ)はことあるごとに「絶望した!」と叫んで首を吊るし(もちろん毎回未遂に終わる)、彼が受け持つクラスメートもひきこもりや過度の几帳面といった
“持ちネタ”には事々かない。登場人物の名前さえ彼らの強烈な個性から言葉遊びで名づけられてい
る。
これだけ聞くと、とても露悪的な作品だと思われてしまいそうなのだが、実際にはそうではない。
登場人物たちの一見深刻な事情は、ギャグ漫画の構成上ツッコミを受けるボケではあるものの、思い悩むような短所としても矯正するべき問題としても描かれていないのだ。ストーカーの少女はずっと自身のストーカー気質を持ちネ夕にするし、ひきこもりの少女もひきこもりという個性を手放すことはない。迷惑のかけあいは日常茶飯事だ。どんな”問題”を抱えた生徒だって、平均的すぎる少女と対等な、あくまで強烈すぎる個性でしかない。
「この作品は、教師は完璧であるべきで、生徒の問題は解決されなくてはならない、という学校教育へのアンチテーゼで・・・・・・」と真面目に捉えるのはきっと拡大解釈なんだろう。それでもこの作品は僕の人生を変えた名著の一つだ。
自分が抱える“問題”を受け入れて、朗らかな持ちネタにするのは面白くて格好いい。そして人に勇気と元気を与える。この作品に出会って、僕はポジティブなあまのじゃくになったと思う。
繋がるゲームから思いを馳せる
もう一つのおすすめ作品は、言わずと知れたスマートフォンアプリ、ポケモンGOだ。最近は新型コロナウィルスの影響で以前ほど見られなくなったが、かつてはマクドナルドの前や何もない公園の隅には談笑するでもなくスマホをずっといじっている学生や主婦、お年寄りなどが集まっていることがあった。僕はその集団の中の一人だった。
先ほどの絶望先生が性格に影響を与えた作品なら、こちらは行動や習慣の面で自分を大きく変えた作品になる。
ポケモンGOにハマった人間によくある症状を紹介していこう。
まず第一の症状として、外出が多くなる。ポケモンGOの世界では外出こそが全てだ。デイリーボーナス(毎日最初にログインした時に手に入るアイテムなどのこと)を受け取るだけでも多少の外出が必要だし、ゲームで開催されるイベントの日ともなると珍しいポケモンを手に入れるために数時自分の個人的な意見としては、社間ずっと歩きっぱなし、というこ会的包摂を何かの目的に据えることもざらにある。
第二の症状は、地域コミュニティとの繋がりができることだ。
伝説のポケモンをゲットするためにマクドナルドや公園に通っているうちに、徐々に顔見知りが増えていくのだ。
ポケモンGOが抱え込んだ多様性は本当に類を見ないもので、地域のグループLINEには学生や主婦や会社員はもちろん、お年寄りや留学生、大学教授やインドカレー屋の店員らしき人物など様々な人が参加していた。
ポケモンGOをプレイする、散歩するという2つの習慣は、うつ病に苦しんでいた頃の自分をよく支えてくれた。日中に散歩する習慣づけは言わずもがな、実家を離れて一人暮らしをしていた自分には、同じゲームをプレイしてできた地域社会との繋がりが特にありがたかった。
社会的包摂(ソーシャルインクルージョン)の重要性が意識される昨今ではあるけれど、あくまで自分の個人的な意見としては、社会的包摂を何かの目的に据えることには多少の懐疑心もある。最初からそれを目的にしていなかったからこそ、既に地域との繋がりがある主婦やお年寄りも参加していたし、包摂や孤立を意識せずに対等な友人になれたのではないかと思う。
社会的包摂のための取り組みも大事だけれど、既にある物事の中に社会的包摂を見出して、それを壊さないように、より大きくしていくことも結構重要かもしれないと思う。
著者 石田彰紀