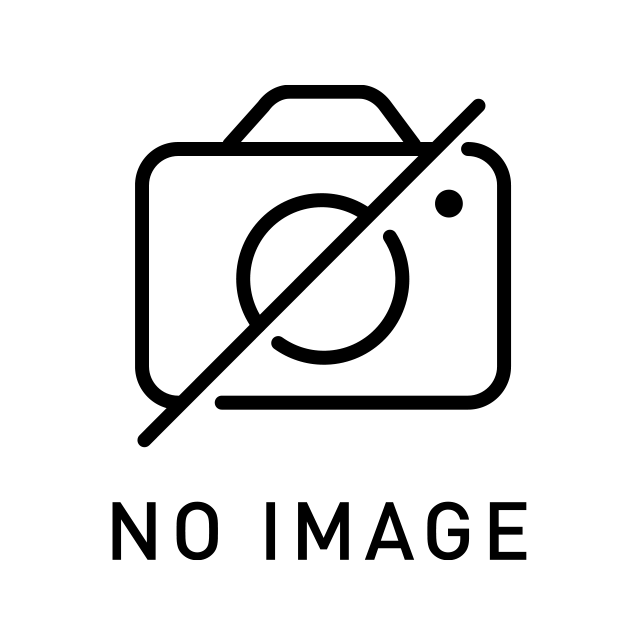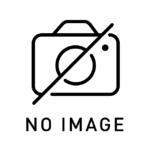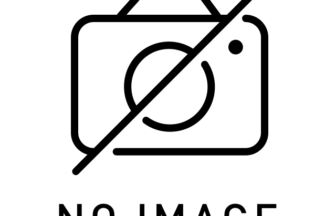寺尾 紀彦
株式会社スピードワゴン代表
京都のベンチャー企業のシステムエンジニアとして勤務し、長男の誕生を機に「家族や地域のためにばる生き方を探そう」と思い大津で起業。
寺尾 伸子
ワノチヱ本舗店長
夫を手伝おうと事業に参加。料理や食品に対するセンスを活かし、現在はワノチヱ本舗の店長を務める。
子供の誕生をきっかけに知った福祉の存在
寺尾紀 元々、京都市に住んでいたんですけど、
子供を授かったタイミングで「一軒家に住みたいね」と夫婦で話し合っていました。そこで色々と探していく中で「自然がたくさんある大津市がいいじゃん」という話になり、大津市に移ってきました。子供が生まれるとその子がダウン症であることが分かりました。そのタイミングで、全国で千以上ある自治体の中で、とりわけ大津市は療育福祉にとても積極的に取り組んでいることを知りました。
寺尾伸 本当にたまたまなんです。妊娠中に京都市から大津市へ見学に来たときには「自然がいっぱいのところだな」という思いから、ここに住みたい.と決めました。療育福祉については長男を産んだ後に知りました。
寺尾紀 障がいを持って生まれた子どもに対して「行政ができることは何だろう」と積極的に関わるような制度を持っているのが大津市でした。福祉施設の方々との間に行政が立っているのと、特に母親へのサポートが手厚い自治体だったので、ありがたいと感じました。
ずっとIT業界にいた僕は、人と関わることに苦手意識があるので、福祉に関わる方々から、進んでサポートしていただけたのはすごくありがたかったです。「自分のような人間に何ができるのか」と考えるようになったのは、やっぱり子供を授かったのがきっかけでした。お医者さんに「お子さんはダウン症です」と言われた時のことは、今でもはっきりと覚えています。「子どもに一生、障がいを背負わせてしまった」という現実に向き合うために、自分のこれまでとこれからを考えなければならないと思いました。
大津で家を建てて「ここで商売をしよう」と決めてから、「自分には何ができるのか」と考え続ける毎日だったので、自然に「家族と地域で生きること」を意識するようになりました。
家族と地域のために生きたいと思い、会社設立
寺尾紀 起業したきっかけは、子どもや家族、地域のために生きていけるような生活をしようと考え、地産地消で滋賀の質の良い素材を使った商品を販売したいと思ったためです。会社設立後に地域の様々な福祉施設を回らせてもらったのですが、「自分は福祉施設で役に立てることはあまりない」という印象を受けました。施設の方々は既にそれぞれで工夫し運営されていたからです。その中でも特に印象に残った事業所は、比叡山の中腹にある牧場で利用者と羊の毛刈りをして、その毛を織って反物を作っていた施設です。
福祉施設に商売のイメージがない現状を変えたかった
寺尾紀 どの施設の取り組みも「すごい」と思いましたが、福祉施設ではあまり商売のイメージがないことが気になりました。僕は、世の中には福祉施設の取り組みや商品を高く評価し、多少高いお金を出してでも購入を希望する人がいるように考えたのです。でも、その時の自分には何かを提案するようなことはできませんでした。
しかし、自分にできることを探すうちに、世界的な影響力のある人が福祉施設の一着数百円で売られている反物に対して、「私、この羊の服が好きなんだ」と言えば、数百万円の価値がつくことがあるのを知りました。
そのような発想から通販ショップの事業を始めました。やがて、福祉施設と連携することを実際に考えたとき、「食べ物を扱うのが分かりやすくていいな」と思ったんです。
食品販売に必要な存在は伸子さん!
寺尾紀 ただ、僕は食べ物を食べることにあまり興味がなくて(笑)。
一方で家内は実家が福岡で、地域の方々との地縁が強く、食べ物を楽しくおいしくいただくということに長けているんです。僕は事業の戦略は考えるのは得意ですが、食べ物の味について具体的なことはよく分かりません。例えば、仕入れをする際は施設に入らせていただく時に、一個一個品質をチェックしているのですが、その作業は家内の方が得意です。家内と協力しながら店長と社長のような関係で進めています。
メニュー開発はここが辛い!手間暇がかかる理由
寺尾伸 メニュー開発をするために家で毎日商品を作っています。作り続けていると、どれが本当の味か分からなくなるときがあります。
寺尾紀 提携先のお店や家で試作するのと、その味を商品化するためにレトルトパウチに詰めて最後に煮沸で焼き上げたものとでは、手順が変わるので味も変わります。そこでパウチ化しても試作品と同じ味になるレシピを見つけるために、家内が作っては見直すという作業をずっとやっています。
寺尾伸 パウチにするための最後の工程で味や風味が変わります。その工程では調理した食材を真空パックに入れて、約100度まで加熱して殺菌します。このとき30分ぐらい熱を加え続けると、家で作った試作品と味が全く変わってしまいます。
パウチ加工用の機械は福岡にあるので、自宅でレシピを練り直し、福岡に指示を送って、現地で作りパウチ化したものを送ってもらって、食べた感想からまたレシピを練り直す、の繰り返しです。
寺尾紀 なので、僕が「商品を増やそう」と言うと、最初は「その作業は誰がやると思つてるん?」と家内から言われたりしました(笑)。
寺尾伸 手間や時間がかかった分、商品の値段も上がります。元々食べ物を買うのが好きなので消費者目線の感覚があり、開発中も最終的な価格が気になって、「購入していただけるかな?」と心紀になります。でも、固定客の方が付き始めると「これは家にかせません」「何個かストックしておかないと不安になります」とレビューで書いてくださることがあるんです。そういう時は、がんばって開発した甲斐があったなと感じます。
製品のこだわりは「付加価値を高める」
寺尾紀 僕自身はメーカーではなく、食べ物を直接育てて作っているわけじゃないので、「製品の付加価値を高める」というのがこだわりであり、うちの仕事だと思っています。
食べ物は「どういうシチュエーションで買うのか」「誰と食べるのか」という付加価値によって商品の値段が変わっていきますよね。自社が作っている商品じゃないからこそ、「どう見てもらうのか」「どういう風に受け取ってもらえるのか」をすごく考えました。ワノチヱ本舗を始めるきっかけになった商品が『発芽玄米めん』でした。たまたま同時期にお米由来の商品二つを施設から預かった際に「日本の主食はお米だし、日本以外ではこういう商品も生まれなかっただろう」と考えました。そこで、当時のデザイナーと「お米にどんな強みがあるのか」を真剣に話し合いました。
僕は自分自身の経験から、障がいの有る無しに関わらず、「自分は誰かにとってかけがえのない存在である」という認識と、社会にどれだけの貢献ができて、どれだけ必要とされているのか、という指標があると、生きていく上で自信になると思っています。
「今日も来てくれてありがとう、助かった」と言ってもらえる職場みたいに、どの人にも社会の中に居場所があってほしいと思っています。そして、その職場は社会から「いいものを作ってくれてありがたい」と思われるような存在であってほしいんです。
例えば、チョークを日本で一番沢山作っている会社が長野にあるんですけど、そこで製造ラインに関わっている人々の約9割が障がいを持つ方なんです。
だから、日本は障がいがあってもなくても関係なくいいものを作ることができる国だと思っています。
ただし、「いいものを作る努力」と「いいものをより高く売る努力」は全く別のものです。だからそれぞれ役割分担が必要なんです。僕は起業してから、「美味しいものを作ることが苦手な自分に何ができるだろうか」ということにずっと向き合ってきました。その結果、美味しいものは家内に作ってもらい、それをなるべく世の中の人たちに見つけてもらって、買ってもらった時に「ああ、良かった」とめてもらえるような仕組みを作っていく、という立ち位置で貢献したいと考えてきました。
福祉を大切にするからこそ「前面に出しすぎない」
寺尾紀 工夫している点として、福祉の側面を出すバランスを大切にすべきだと思っています。福祉を前面に出しすぎてしまうと、「福祉だから商品も安く売ってあるのだろう」「品質はともかく気持ちが大事なので、募金感覚で買わせてもらうよ」といった思いで来られる方が少なからずいらっしゃいます。通販サイトや百貨店などに卸させていただく時は、求められない限りは福祉との兼ね合いの部分は表に出すべきではないのかなと思っています。もちろん隠すことではないですが、言わなきゃいけないことの優先順位としては「食べ物の価値」や「美味しさ」、「どういうニーズの方に食べていただきたいか」という部分がより高いと考えています。
一方で、子供の障がいを親が隠していた昔の時代のように、福祉との繋がりを出さないようにしすぎるのも違うと思います。「チャンネルごとに何を発言すべきかを見極めて、発できるようにならないといけない」という点が苦労しているところであり、これからも工夫を重ねていくところだと思っています。
夢に向かう、地域との繋がり
寺尾紀 来年中には大津市の商店街に実店舗を展開することを検討しています。今は商品がふるさと納税の返礼品に認定され、市が行っている観光振興や商店街の活性化に関する話も進めているところです。そこでECサイトに加えて人に来てもらえる実店舗があれば、市との話し合いの中でより自由な提案ができるのではと考えました。ちょっとずつ認知が広まり人々に広く興味を持っていただいて、様々なことに挑戦していきたいです。最初は、付加価値を付けて福祉施設の価格帯より高く売って人に買ってもらえる根拠はなかったんです。ただ、「他にもその方法で成功しているところがあるということは、うちでもきっと成功する方法はあるだろう」とは思っていました。福祉業界の方々とお話していると、民間企業と比べて優先すべき部分が全く違うことを感じます。何かを始めることによるリスクは、やはりこちらが負うべきなんです。それによってお話を聞いてくださる施設側の方がちょっとずつ増えてくると、色んな新しいチャレンジをやっていけると考えています。
お子さんもB型作業所で活き活き実習!
寺尾伸 子供は高校3年生なので、来年から仕事を始める年齢になります。今はB型作業所へ実習に行っています。
寺尾紀 まだ将来そこで働くとは決まってないのですが、度々お世話になってる施設で、プリンのようなお洒落な洋菓子を作っています。
寺尾伸 普段は甘いものは食べないのに、私が作業所のお迎えに行った帰りに「プリン買って帰ろっか」と言うと「うん!これとこれ!」って選んで、家で食べるときに「僕が作った」と弟に自慢してます(笑)。
寺尾紀 自分が働いているところで作られた食べ物が褒められて、得意げにしている様子を見ていると、僕も嬉しいです。自分達もそういう気持ちで取り組んでいるつもりだったので、ありがたみがすごく分かりますし、いい刺激になると思います